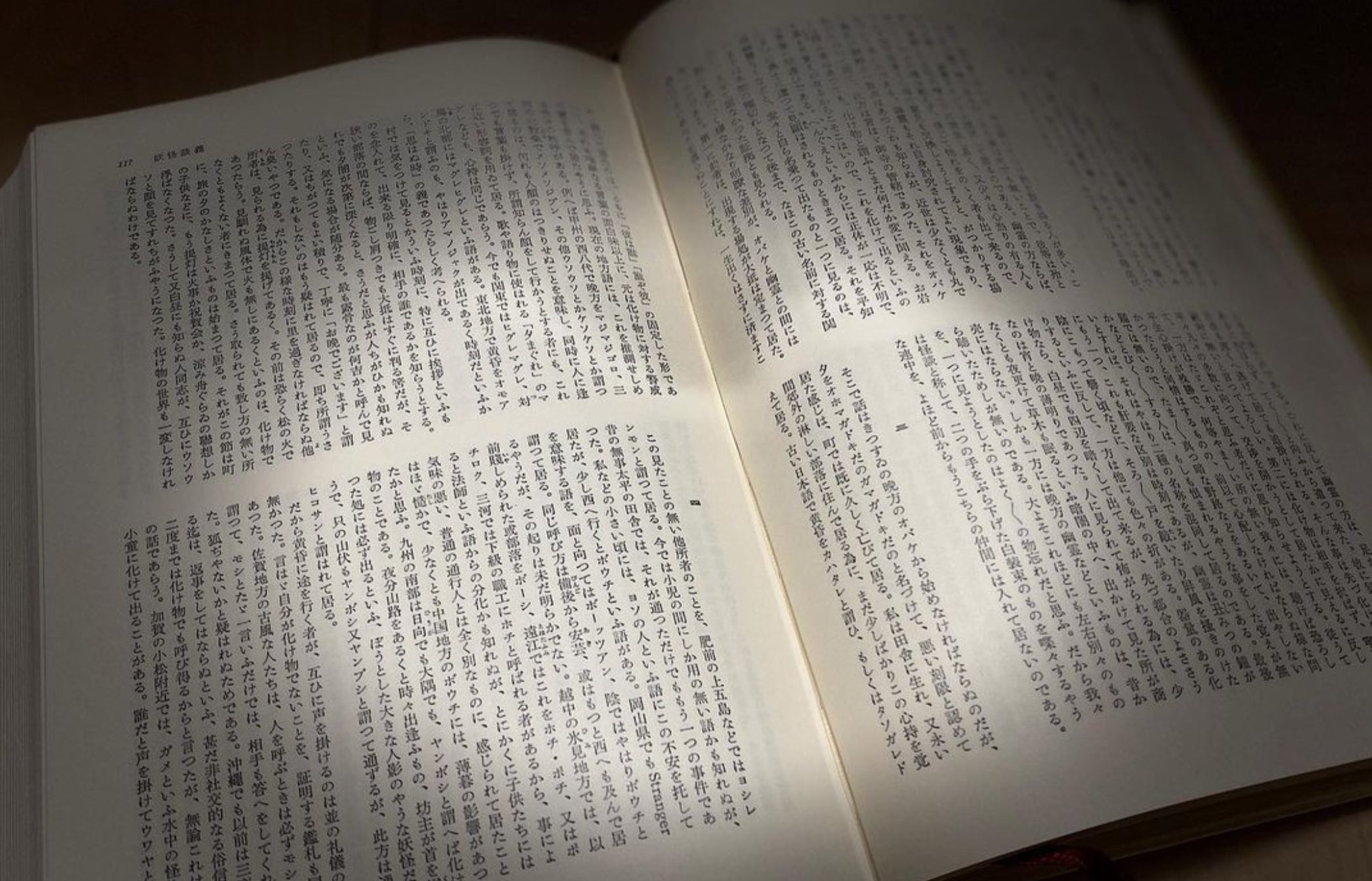産卵期のアユ。四万十川にて。
「僕は魚の中でアユが一番好き!」
先月、川の授業中に四万十高校の男子生徒がそう言い放った。アユの味がとても好きだそうな。「他にも美味しい魚がいるよ」と問いかけようとして思いとどまった。生徒の言い放ち方がかっこよく、とても美味しいアユを食べたのだろうと思い直したのである。
アユの味といえば、県友釣連盟主催の「清流めぐり利き鮎会」があまりに有名だ。全国の清流から集まるアユの食べ比べ。昨年は、県内13河川を含め、過去最多となる28都道府県63河川から寄せられ、グランプリに岐阜県の和良川、準グランプリに須崎市の新荘川など8河川が選ばれた(2019年9月14日)。
数年前、利き鮎会で北海道の河川のアユが選ばれ、その時に来高されていた北海道大学の教授がとても喜んでいたと友人から聞いた。地元のアユが選ばれたということは、その川の環境や人の関わりが良い評価を受けたことにもつながるのだから。
アユと人の関わりには長い歴史がある。『古事記』や『万葉集』には瀬でアユを釣る風景が記されている。また、1845年に土佐藩主の山内豊煕が幡多地域を巡視した際、夕食にアユの「煮浸し」を食べたという古文書も残っており(7月31日)、四万十市郷土博物館で10月27日まで開催されている企画展「鮎の塩焼き篇」でみることができる。
アユは河川生物の中で最も注目を受ける種だ。詳細はアユ研究者である高橋勇夫氏らの書籍を読んでいただくとして、「食性」「なわばり」「魚道」「産卵場造成」など生態工学研究が進んでいる。また、「冷水病」などの水産研究、「友釣り」「火振り」「鵜飼い」などの漁法文化と観光経済効果、「コンフィ」「活魚輸送」などの商品開発まで、多方面から知見の集積と応用が進められている。やはり、その姿や食味にスター性があるのだろう。テナガエビ類を指標にして川をみている筆者からするとアユは眩しい存在である。
アユの味は、川の味。アユと付着藻類の関係も面白い。河床の石には、珪藻や藍藻などが付着している。珪藻はガラス質の殻をもつ藻類で、藍藻はタンパク質を多く含む藻類である。茨城大学の阿部信一郎氏らの研究によると、実験的にアユを除いた河川では常に珪藻が多く優占し、アユを収容した河川では珪藻が著しく減少して糸状藍藻の割合が増加していた。珪藻が剥ぎ取られても糸状藍藻は基部が残って回復しやすい。藍藻はカロリーが高く、アユの成長速度も早いそうだ。釣り師が言う「磨かれた石」は、砂泥がかぶっておらず、アユに捕食されて珪藻が減少し、糸状藍藻が維持されている石なのだろう。
熊本大学の皆川朋子氏らの研究では、洪水などにより河床の石が転倒して石の入れ替わりが生じないと、河床付着物中の細粒土砂量が増加し、藍藻類が減少してアユの餌としての質が低下する可能性が示唆されている。条件にもよるが「転がる石には良いコケがつく」のかもしれない。
河床をつくる土砂は流域の山から供給される。今日は山の日。朝から川に入り、夜はアユの味を堪能して、背景にある山を想うのも良さそうだ。
20200810 高知新聞 寄稿